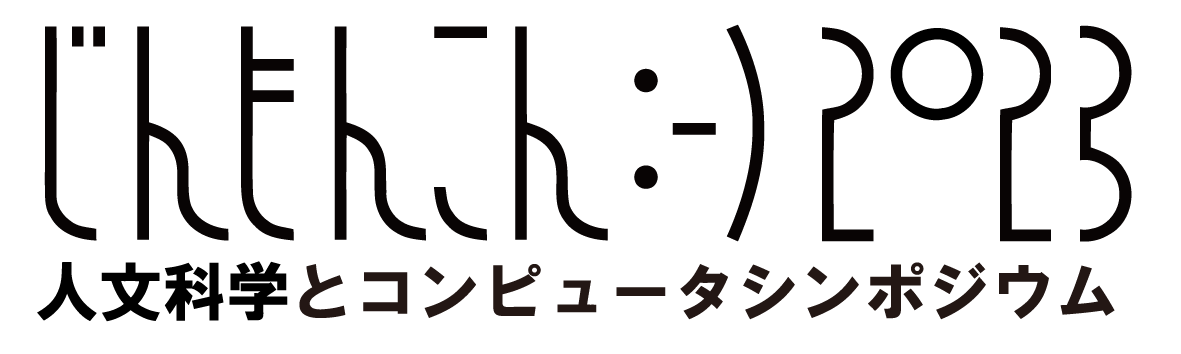お知らせ
じんもんこん2023最優秀論文賞
B-2-1: タイム・リゾルバ ― 時間名リソースからの時間範囲取得 関野 樹(国際日本文化研究センター)
じんもんこん2023学生奨励賞
- I-1-8: 花押を対象とした画像検索システムの改善の試み 石村 隆博(和歌山大学), 北國 智己(和歌山大学), 村川 猛彦(和歌山大学)
- B-3-1: 文学館の Web サイト調査をとおしたデジタル化の状況と課題 関根 颯香(筑波大学), 宇陀 則彦(筑波大学)
- B-3-3: 西浦田楽の保存・継承支援のための映像視聴システムの試作と評価 飯田 悠太(静岡大学), 杉山 岳弘(静岡大学)
じんもんこん2023ベストインタラクティブ発表賞
- I-1-4: 歴史マイクロナレッジの提唱とHIMIKO(Historical Micro Knowledge and Ontology)システムの実装 小川 潤(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター), 大向 一輝(東京大学), 北本 朝展(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)
趣旨
オープンサイエンスの進展とともに、その基盤となる研究データのインフラストラクチャー(インフラ)構築が着々と進められている。研究データインフラに求められるのは、研究成果の検証可能性を担保する機能だけでなく、そのデータを元にしたさらなる発展的な研究の展開や社会へのアウトリーチなど、様々なものが考えられる。それを実現していくためには、構築・運用のしやすい簡潔なメタデータ構造とともに、必要に応じて専門知につながる深い情報という、相反する要素が求められることになる。デジタル時代の研究資料たるデータに様々な文脈から多様な専門知が埋め込まれる人文学においては、この課題はより切実なものとして現前しつつある。すでに海外では、欧州におけるDARIAH(Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities)やCLARIN(Common Language Resources and Technology Infrastructure)等の人文学向けデジタルインフラや、さらにそれを社会科学と統合したSSHOC(Social Sciences and Humanities for the European Open Science Cloud)に見られるように、着々と整備が進められ、大きな広がりを見せている。そして、それを支える枠組みとして、TEI(Text Encoding Initiative)ガイドラインに準拠したテキストデータの構造化やIIIF (International Image Interoperability Framework)によるアノテーションなどの国際標準的なルールが整備され、一方で、TaDIRAH(The Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities)による研究活動の語彙設計など、草の根的な活動も貢献する形となっている。
日本でも、日本学術振興会においては人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業が推進され、人間文化研究機構からはnihuBridgeが公開されるなど、人文学におけるデータインフラは徐々に基礎が固められつつある。こうした動向はどちらかと言えば横断性を重視したものとして広く様々な関心から人文学の研究データに関心を持ってもらい、それを通じて社会に貢献していくことが期待される。一方で、個々のデータを適切に活用するためには、データが作成されたコンテクストやそこに含まれる意味のある情報を適切かつ簡潔に利用者に伝えることが課題となる。技術的には、上述のIIIFやTEI等、国際的な枠組みに基づく取組みが国内でも広がりつつあり、TaDIRAHの日本語版も公開されている。しかしながら、こうした動向は、人文学の様々な分野における方法論の多様さを踏まえるなら、まだ端緒についたばかりである。今後、より多くの分野・方法論に対応できるようなデータの構築方法や、一方で、より効果的な横断的データ探索の手法、そして、そこに対応可能な成果の提示の仕方など、課題は山積している。すなわち、デジタル時代を踏まえた人文学の成果を共有するための適切な枠組みの構築とその普及は喫緊のテーマとなっている。この状況を踏まえ、本シンポジウムでは、「人文学のためのデータインフラストラクチャー構築に向けて」というテーマを設定したい。国内外の様々な研究活動を広く横断しつつ深く提示する研究を踏まえ、国際的にも広く展開できる基礎の構築につなげ、これをもって国内でのプレゼンス向上にも寄与できる大会としたい。
開催概要
日程
2023年12月9日(土)〜10日(日)
会場
オンライン開催(拠点) 一般財団法人人文情報学研究所
共催
一般財団法人人文情報学研究所
後援
実行委員会
下田正弘(武蔵野大学)[委員長]
青野道彦(一般財団法人人文情報学研究所)、小川潤(人文学オープンデータ共同利用センター/東京大学)、苫米地等流(一般財団法人人文情報学研究所)、永崎研宣(一般財団法人人文情報学研究所)、橋本雄太(国立歴史民俗博物館)
プログラム委員会
土山玄(お茶の水女子大学)【委員長】
大向一輝(東京大学)、亀田尭宙(国立歴史民俗博物館)、耒代誠仁(桜美林大学)、北本朝展(国立情報学研究所)、小風尚樹(千葉大学)、鹿内菜穂(亜細亜大学)、堤智昭(筑波大学)、吉賀夏子(大阪大学)、李媛(関西大学)
主なトピック
人文科学とコンピュータ研究会の理念に即したテーマについての研究発表・事例報告などについて広く歓迎いたします。具体的なトピックは以下に挙げますが、この限りではありません: デジタル・アーカイブ(記録、保存もしくは活用に関する技術、事例、理論など)、保存科学、文化財防災、MLA連携、デジタル博物館、デジタル化文書、ドキュメンテーション、考古学・歴史学・文献学・言語学などの人文系諸学を含むデジタル・ヒューマニティーズ、人文情報学、時空間情報、視覚化、データ・マイニング、色彩情報処理、情報技術を用いた教育、WEB活用、情報検索、メタデータ、知的財産権・著作権課題など、広く 人文科学とコンピュータ研究会の理念に即したテーマ、事例、現状批判、問題提起などについてのご発表も広く歓迎いたします。
発表論文募集
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 募集開始 | |
| 概要論文締切 |
|
| 論文採否通知 | |
| カメラレディ論文締切 | 2023年11月4日(土) 23:59(JST)必着 |
概要論文の応募について
-
A4判2ページ(図表を含む)の概要論文を作成してください。
査読方針、概要論文の書き方、送付方法などについては、 以下のフォーマットに詳しい情報がありますので、 ダウンロードの上、必ず参照してください。 -
2023年度、
じんもんこんシンポジウムはシングルブラインド制を採用します。 著者・所属も概要論文に記載をお願いします。 -
概要論文には希望する発表形式(口頭、インタラクティブ、
どちらでもよい)を明記してください。 -
原則として筆頭著者および発表者となれるのは、
企画セッションを除いて著者一人につき1発表とします。 共著者には特に制限はありません。 -
学生が第1著者の場合は、学生奨励賞の審査対象となりますので、
審査希望の有無を選択してください。 -
提出された概要論文に基づいて、プログラム委員会で査読・
審査の上、応募論文の採否を決定します。 -
採択された場合、
A4判6ページか8ページの論文集用カメラレディ論文を提出して
いただきます。
発表形式
- 下記のツールを利用した オンライン発表を予定していますが、状況の変化により若干方式が変更になる可能性があります。
口頭発表
- Zoomによるオンライン発表になります。 1発表につき質疑を含めて合計30分程度となります。
- 詳しくは 口頭発表要領をご確認ください
- 1本あたり発表時間20分、質疑応答5分の計25分(入れ替え含む)です。
インタラクティブ発表
- じんもんこん2023では、ポスター・デモセッションに代わり、インタラクティブセッションを実施します。 1発表1分間のライトニングトークと、 ポスター相当のPDFをご用意ください。それから、任意提出で5分以内の説明動画(後述)も受け付けています。 コアタイムには、オンラインツール(詳細は参加者向け頁をご覧ください)を用いて質疑応答を行います。 ポスター・デモセッション(コアタイム)で、Zoomにより、 Zoom(ビデオウェビナー)により、1発表につき1分間のライトニングトーク(ポスター・デモ紹介)を行います。
- インタラクティブセッション発表者には、任意で、5分以内のポスターないしデモの説明動画を 事前に録画していただき、それを参加者が大会開催期間中に閲覧できるようにします。 これは、参加者の間により広く発表内容を知らしめることを希望する発表者のための手立てとなります。これにより、より多くの参加者が、都合の良いタイミングで発表を把握し、それを踏まえて発表者と質疑応答できることになります。
プログラム
アクセス情報
参加申込
申込方法
早期申込み割引は12/1(金)までです!
情報処理学会の
申し込みフォーム
からのお申込みになります。参加費についてはそちらでご覧ください。なお、本シンポジウムでは、各発表に対して1名以上の有償での参加登録をお願いしております。
論文集は印刷版、ダウンロード版の両方を提供いたしますが、会期までに印刷版の入手をご希望の方は、11月末日までにマイページでの参加登録を完了ください。
※学生(論文集なし)の方は
専用のフォーム
より参加登録ください。
問い合わせ
jmc2023■dhii.jp(■を@に変えてください)