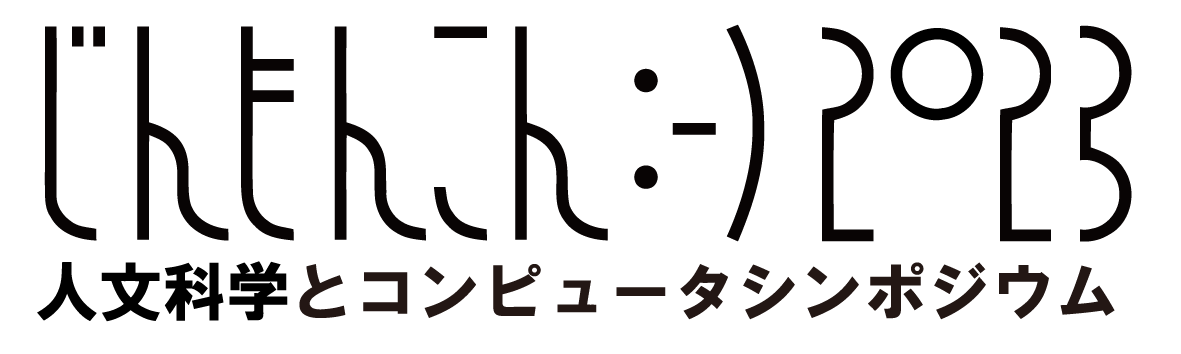プログラム
研究発表、その他のセッションに色分けしています。
2023年12月9日(土)
| Zoom会場 A | Zoom会場 B | oVice会場 C | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15~09:30 オープニング |
S-1:オープニング | |||
| 09:30~11:00 口頭セッション1 |
A-1:テキスト解析1 | B-1:画像処理 | ||
| 11:00~11:10 | 休憩(10分) | |||
| 11:10~12:40 口頭セッション2 |
A-2:テキスト解析2 | B-2:基盤構築 | ||
| 12:40~14:00 | 休憩(80分) | |||
| 14:00~15:00 基調講演 |
基調講演 | |||
| 15:00~15:15 | 休憩(15分) | |||
| 15:15~15:30 インタラクティブプレゼン1 |
I-1:インタラクティブプレゼン | |||
| 15:30~17:00 インタラクティブディスカッション1 |
I-1:インタラクティブディスカッション | |||
| 17:00~17:15 | 事務連絡 | |||
| 17:15~19:30 | 懇親会 | |||
2023年12月10日(日)
| Zoom会場 A | Zoom会場 B | oVice会場 C | |
|---|---|---|---|
| 09:30~11:00 口頭セッション3 |
A-3:言語 | B-3:デジタルアーカイブ | |
| 11:00~11:10 | 休憩(10分) | ||
| 11:10~12:40 口頭セッション4 |
A-4:テキスト構造化 | B-4:情報基盤 | |
| 12:40~14:00 | 休憩(80分) | ||
| 14:00~15:30 企画セッション |
企画セッション | ||
| 15:30~15:45 | 休憩(15分) | ||
| 15:45~16:00 インタラクティブプレゼン2 |
I-2:インタラクティブプレゼン | ||
| 16:00~17:30 インタラクティブディスカッション2 |
I-2:インタラクティブディスカッション | ||
| 17:30~17:45 クロージング |
クロージング | ||
口頭セッション1 A-1:テキスト解析1
12月9日(土) 09:30~11:00Zoom会場 A
座長:土山玄(お茶の水女子大学)
- A-1-1: 現代怪談における結末の類型化と物語構造及び怪異特徴の比較分析
大田 翔貴(公立はこだて未来大学), 村井 源(公立はこだて未来大学) - A-1-2: 物語の展開パターンの結合の特徴に基づく構造の自動生成-『ブラック・ジャック』新作に向けて
村井 源(はこだて未来大学), 青山 美月(はこだて未来大学), 大田 翔貴(はこだて未来大学), 大場 有紗(はこだて未来大学), 福元 隆希(はこだて未来大学), 奥山 凌伍(はこだて未来大学), 金刺 智哉(はこだて未来大学), 富田 真生(はこだて未来大学), 入舩 真誠(はこだて未来大学), 坂本 珠凜(はこだて未来大学), 吉井 史夏(はこだて未来大学) - A-1-3: 歴史災害史料からの自動地名抽出に向けた自然言語処理システムの性能評価
武内 樹治(立命館大学), 大内 啓樹(奈良先端科学技術大学院大学), 東山 翔平(国立研究開発法人情報通信研究機構)
口頭セッション1 B-1:画像処理
12月9日(土) 09:30~11:00Zoom会場 B
座長:亀田尭宙 (国立歴史民俗博物館)
- B-1-1: 深層学習による木簡欠損部位の画像復元
塩野 健治(東京電機大学), 大山 航(東京電機大学) - B-1-2: IIIFを用いた前近代絵図の比較支援ツールの開発
中村 覚( 東京大学), 黒嶋 敏(東京大学), 畑山 周平(東京大学), 山田 太造(東京大学) - B-1-3: そあん(soan):古活字データセットを用いた現代日本語テキストからくずし字画像への変換と共有
北本 朝展(ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センター, 国立情報学研究所), 本間 淳(フェリックス・スタイル), カラーヌワット タリン(Google DeepMind)
口頭セッション2 A-2:テキスト解析2
12月9日(土) 11:10~12:40Zoom会場 A
座長:村井源 (はこだて未来大学)
- A-2-1: クラスタリングを利用したキーワード抽出アルゴリズムのツイッターデータへの適用例
宇野 毅明(国立情報学研究所), 橋本 隆子(千葉商科大学) - A-2-2: What if War in Taiwan--Applying Machine Learning to Analyze the Resist Will
Shao Hsuan-Lei(National Taiwan Normal University)
口頭セッション2 B-2:基盤構築
12月9日(土) 11:10~12:40Zoom会場 B
座長:吉賀夏子(大阪大学)
- B-2-1: タイム・リゾルバ ― 時間名リソースからの時間範囲取得
関野 樹(国際日本文化研究センター) - B-2-2: 古辞書データベースの開発
藤本 灯(清華大学), 劉 冠偉(東京大学), 久保 柾子(総合研究大学院大学, 学振), 大島 英之(東京大学, 学振) - B-2-3: S×UKILAM 教材アーカイブの LOD 化:RDF と SPARQL によるデジタルアーカイブを 活用した教材と多様な教育情報の接続・構造化
大井 将生(人間文化研究機構, 東京大学), 中村 覚(東京大学), 大向 一輝(東京大学), 渡邉 英徳(東京大学)
基調講演
12月9日(土) 14:00~15:00Zoom会場 A
激変する知識環境とDigital Humanitiesの未来
――研究としてのインフラストラクチャー構築――
下田正弘(武蔵野大学教授/一般財団法人人文情報学研究所代表理事/東京大学名誉教授)
知識環境におけるDXとAI化という二つの激流を受け、あらゆる学知が、その構築方法において大きな方向転換を迫られている。この未曾有の状況にあって切実な課題は、もはやこの変化の埒外に身を置こうとする伝統的人文学からの応答ではないだろう。むしろこの命運を担おうとする人文情報学Digital Humanitiesこそが、これまでの歩みを再考しつつ、自身の使命と意義とを更新し、あらたな地平に定位しなおしゆくことにある。本講演では、こうした問題状況を共有し、今後、ともに向かうべき方向を模索したい。
インタラクティブプレゼン&ディスカッション1
12月9日(土) 15:15~15:30Zoom会場 A,
15:30~17:00oVice会場 C
座長:鈴木親彦(群馬県立女子大学)
- I-1-1: 日本語方言談話資料のTEIによる構造化の試み
中川 奈津子(国立国語研究所), 岡田 一祐(慶応義塾大学), 永崎 研宣(人文情報学研究所), 北﨑 勇帆(大阪大学), 王 一凡(人文情報学研究所, 東京大学), 曹 芳慧(大阪大学), 藤原 静香(京都女子大学), 塚越 柚季(東京大学), 乙川 文英(定光寺), 小川 潤(ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センター, 東京大学), 片倉 峻平(東京文化財研究所), 左藤 仁宏(東京大学), 王 雯璐(東京大学), 石田 友梨(岡山大学), 宮川 創(国立国語研究所), 佐久間 祐惟(東京大学), 塩井 祥子(早稲田大学), 井上 慶淳(龍谷大学), 村瀬 友洋(SAT 大藏經テキストデータベース研究会), 関 慎太朗(東京大学), 田良島 哲(東京国立博物館),嵩井 里恵子(パリ・シテ大学), 渡邉 眞儀(東京大学, 浄土宗総合研究所), 中町 信孝(甲南大学), 幾浦 裕之(国文学研究資料館) - I-1-2: ジャン=ジャック・ルソーのジュネーヴ手稿を対象としたデジタル批判版の試作
飯田 賢穂(筑波大学), 中村 覚(東京大学), 淵田 仁(城西大学) - I-1-3: TEIに準拠した近代短歌テキストのマークアップ手法の提案
村田 祐菜(国立国会図書館), 永崎 研宣(人文情報学研究所) - I-1-4: 歴史マイクロナレッジの提唱とHIMIKO(Historical Micro Knowledge and Ontology)システムの実装
小川 潤(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター), 大向 一輝(東京大学), 北本 朝展(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) - I-1-5: Transcribing and analysing Seventeenth-century English primary sources with Transkribus
槙野翔(ダブリン大学トリニティ・カレッジ) - I-1-6: 中尾佐助スライドデータベースにおける RDFに基づく主語・述語・目的語をキーとした SPO検索システムの開発
宮地 悠人(大阪公立大学), 小島 篤博(大阪公立大学) - I-1-7: ブロックチェーン技術に基づく資料流通記録システム
磨 有祐実(大阪大学), 山田 憲嗣(大阪大学), 中山 文(神戸学院大学), 谷田 純(大阪大学) - I-1-8: 花押を対象とした画像検索システムの改善の試み
石村 隆博(和歌山大学), 北國 智己(和歌山大学), 村川 猛彦(和歌山大学) - I-1-9: 災害ナラティブのオンライン収集とマッピング:西日本豪雨の被災地を事例に
内尾 太一(静岡文化芸術大学) - I-1-10: 居住地域と環境配慮行動の意思決定過程との関係性について
石井 康平(千葉大学)
口頭セッション3 A-3:言語
12月10日(日) 9:30~11:00Zoom会場 A
座長:高田智和 (国立国語研究所)
- A-3-1: ニューラル機械翻訳を使った中国語古文の翻訳-訓練・評価時の時間的差異の検証
段 文傑(東京都立大学), 王 鴻飛(東京都立大学), 岡 照晃(東京都立大学), 小町 守(一橋大学), 古宮 嘉那子(東京農工大学) - A-3-2: 漢字構造検索機能の IPFS 化の試み
守岡 知彦(国文学研究資料館) - A-3-3: 『日本書紀』Universal Dependenciesへの挑戦
安岡 孝一(京都大学), ウィッテルン クリスティアン(京都大学), 守岡 知彦(国文学研究資料館), 池田 巧(京都大学), 山崎 直樹(関西大学), 二階堂 善弘(関西大学), 鈴木 慎吾(大阪大学), 師 茂樹(花園大学), 藤田一乘(京都大学)
口頭セッション3 B-3:デジタルアーカイブ
12月10日(日) 9:30~11:00Zoom会場 B
座長:山田太造(東京大学)
- B-3-1: 文学館の Web サイト調査をとおしたデジタル化の状況と課題
関根 颯香(筑波大学), 宇陀 則彦(筑波大学) - B-3-2: 舎利容器のデジタルコンテンツ ~博物館における常設展示を目的とした体験型システムの改良と運用~
中池 天音(龍谷大学), 阪口 直樹(龍谷大学), 曽我 麻佐子(龍谷大学) - B-3-3: 西浦田楽の保存・継承支援のための映像視聴システムの試作と評価
飯田 悠太(静岡大学), 杉山 岳弘(静岡大学)
口頭セッション4 A-4:テキスト構造化
12月10日(日) 11:10~12:40Zoom会場 A
座長:堤智昭(筑波大学)
- A-4-1: OCRの高精度化を踏まえたデジタル学術編集版の新展開
永崎 研宣(一般財団法人人文情報学研究所), 大向 一輝(東京大学), 下田 正弘(武蔵野大学) - A-4-2: 勅撰和歌集の構造化と提示手法に関する試み ―嘉禄二年本『古今和歌集』を事例として―
幾浦 裕之(国文学研究資料館), 永崎 研宣(人文情報学研究所), 加藤 弓枝(名古屋市立大学) - A-4-3: ドゥームズデイ・ブックのテキスト生成過程分析のためのビューワ開発
小風 尚樹(千葉大学), 中村 覚(東京大学), David Roffe(Institute of Historical Research), 鶴島 博和(熊本大学)
口頭セッション4 B-4:情報基盤
12月10日(日) 11:10~12:40Zoom会場 B
座長:関野樹(国際日本文化研究センター)
- B-4-2: Quantitative Evaluation of Local Distortion in Historical Maps by Using the Nabla Operator
Miura Takeshi(Akita University) - B-4-3: 組合せ最適化に基づく文字解読への確率モデルの導入
楉 春華(奈良女子大学), 吉田 哲也(奈良女子大学) - B-4-1: NDLTableSet:デジタル化資料中の表領域の構造化を目的としたデータセットの構築及び機械学習手法の検討
青池 亨(国立国会図書館)
企画セッション
12月10日(日) 14:00~15:30Zoom会場 A
オンラインワークショップ「DH教育とリテラシー」
インタラクティブプレゼン&ディスカッション2
12月10日(日) 15:45~16:00Zoom会場 A,
16:00~17:30oVice会場 C
座長:鹿内菜穂(亜細亜大学)
- I-2-1: 行政文書のやさしい日本語翻訳におけるChatGPTの活用の可能性
鈴木 ミユキ(静岡大学), 杉山 岳弘(静岡大学) - I-2-2: 自己呈示スタイルの日中文化比較 -自己評価・欲求・行動方略の観点から-
徐 韵(同志社大学), 阪田 真己子(同志社大学), 坂本 晶子(ワコール人間科学研究開発センター) - I-2-3:
インドネシア語における語彙アスペクトの自動判別
佐近 優太(東京大学, 日本学術振興会) - I-2-4: 正徹本『源氏物語』の用字の調査 − 仮名字母と本文表記を中心として −
齊藤 鉄也(淑徳大学) - I-2-5: データマイニングによる『論理哲学論考』の邦訳における訳語の類似性分析
井上 颯樹(千葉大学), 亀田 尭宙(国立歴史民俗博物館), 小風 尚樹(千葉大学) - I-2-6: 形態素解析ツールWeb茶まめによるコーパス作成支援
堤 智昭(筑波大学), 中村 壮範(国立国語研究所), 小木曽 智信(国立国語研究所) - I-2-7: 『古今集遠鏡』コーパスの設計と構築
久保 柾子(総合研究大学院大学), 市村 太郎(京都府立大学), 小木曽 智信(国立国語研究所) - I-2-8: オープンソース漢字字形管理システムhi-glyphの開発と応用
劉 冠偉(東京大学), 中村 覚(東京大学), 山田 太造(東京大学) - I-2-9: くずし字学習アプリケーション「百人一首デジタル教材」の開発とその活用
林 愛梨(大阪工業大学), 須永 宏(大阪工業大学), 横山 恵理(大阪工業大学) - I-2-10: 推理小説における作家固有の伏線とオチ,シーンとの関係についての傾向の分析
青山 美月(公立はこだて未来大学), 村井 源(公立はこだて未来大学) - I-2-11: 陳昌治本『説文解字』中華書局影印本の加筆箇所
鈴木 俊哉(広島大学)